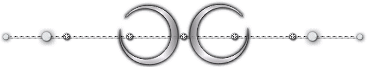 |
| Whirlwind (原案・設定・構想) Aileen・kujidon・shima・瑠衣 (本編構想) shima 第4話 気になること 歓迎会の次の日、もう昼を過ぎたというのに、マヤはまだ布団から出られないでいる。 確かに二日酔いで頭痛もするが、悩まされてるのはそれだけではない。 頭の中をかけめぐるのは、歓迎会でしてしまった失敗のことばかりだ。 「もういやぁー!!」 あれやこれや朧げな記憶をたどり、ついに速水に抱きかかえられて帰宅したところまでたどり着くと、あまりの恥ずかしさに思わず声を上げてしまった。 安普請のアパート中に聞こえてしまったかもしれない。 どこからか苦情の声が聞こえてくるかも…と構えていると、突然電話が鳴った。 「起きてた? よかったらこれから出てこない?」 店に着くと、 姫川亜弓はすでに奥のソファにかけており、テーブルには色とりどりのケーキが並べられていた。 「これって、いつもの?」 マヤが尋ねると、亜弓は困ったように微笑んだ。 いつもこうなのだ。 亜弓はその美貌のため、どこに行っても特別扱いを受ける。 店の中を見渡せば、この席は一番話のしやすい奥まった場所にあるし、ケーキもおそらくはこの店の従業員にサービスされたものなのだろう。 しかし、亜弓はほっそりとした外見とはうらはらに、ちょっとしたことで太りやすい体質らしい。 もちろん儀礼的に一口二口は手を付けるが、残りは食べても食べても太らないマヤの胃の中におさめられてしまうのが常だ。 ケーキをほおばるマヤとは対照的に亜弓は優雅に紅茶を飲む。 その姿の、自分とのあまりの違いに、マヤは思わずため息がこぼれそうになる。 亜弓に初めて会った日… 教育実習初日に、案内された部屋の中で光輝く彼女を見た時には、世の中にこんな奇麗な女の子がいるものなのか…!と本当に驚いた。 しかし、マヤの何を気に入ったのか、彼女はマヤを夕食に誘い、それをきっかけに、教育への熱い想いという共通点を持つ二人はすぐに意気投合してしまった。 それ以来、マヤは国文学、亜弓は英文学と専攻も大学も別であり、勤務先も紅学園とオンディーヌ学園とに別れてしまったにもかかわらず、親友であり続けている。 「それで、どうだったの学校の方は?」 亜弓は待ちきれないかのように身を乗り出す。 マヤがしぶしぶながら、初日からの顛末を話しだすと、最初は遠慮していた亜弓もクスクス笑い出した。 「速水先生って、私も名前は知っているわよ。紅学園にびっくりする程美しい男性教師がいるって。しかも長身で頭が切れる…。 オンディーヌでも狙っている女性は多いみたいだけど、一番執着しているのは鷹宮紫織先生のようね。速水先生には相手にされてないって話だけど。そもそも人間嫌いというか…そんな冷たいところも人気の理由みたい」 「人間嫌い?」 「ええ。誰にも心を開こうとしないっていう噂だわ」 亜弓はそう答えてから、不思議そうな顔をする。 「でも、マヤの話を聞いているとなんだか別人のような気もするわね。まぁオンディーヌには若い男性教師が少ないのよ。 唯一若くてかっこいい先生にも、すっかり奥さん気取りの彼女がいるし。 紅学園は速水先生の他にも、素敵なひとが多いってオンディーヌの女性たちはうらやましがってるのよ」 「だけど、亜弓さんは男は顔じゃないんでしょ?」 「そうよ。うちは母がそういうポリシーだから」 マヤはいつか紹介された、身なりにかまわない芸術家風の亜弓の父とまるで女優のような母を思い浮かべる。 どこかの学校を経営しているという話だったが、亜弓が詳しく話さないので、マヤも聞いたことはない。 彼女は両親をとても尊敬しているらしく、その考え方にも大いに影響を受けているようだった。 「歓迎会が同じお店だったなんて、全然知らなかったわ。 私、理事長と学園長に挟まれてて身動きとれなかったのよ。他の先生方ともほとんど話せなかったの」 「あたし、亜弓さんに送ってもらえればよかったのにな」 「そんなに酔ってたの?」 速水に送ってもらったことを聞くと、亜弓はそれまで笑っていた表情を曇らせた。 「ええっ! 抱きかかえられて帰って来たの? そんな…眠ってしまって男の人と二人きりだなんて、何があってもおかしくないのよ?」 「そ…そうだけど…」 予想外に激しく叱責されてしまい、マヤは話したことを後悔した。 「そのうえ記憶もないなんて! 大丈夫なの? マヤったら…」 何事にもきちんとしている亜弓にとっては、マヤの失敗談には驚かされることが多い。 亜弓もそれを楽しんでいる部分があるにはあるが、これはその範疇を超えている。 「そうよね…私もしっかりしなきゃ。教師なんだし」 (落ちこんでばかりいられないわ…来週からは、もう絶対失敗しないように頑張らなきゃ!) 親友に話したことで、一人でウジウジ悩んでいるよりは、先にすすめたような気がしたマヤだった。 すっかり遅くなってしまったが、まだまだ喋り足りない二人は名残を惜しむように、帰り道をゆっくりと歩いた。 いつも互いの家を結ぶ中間点で会うことになっているので、ホームまでは一緒の道のりだ。 ふと亜弓が意味深に笑う。 「でもね、うふふ。マヤが男の人のことで、そんなにムキになっているのって、初めて見たかもしれないわね」 「えー。そんなことない…と思うけど…」 予想もしなかったことを指摘され、頬は熱を帯び、赤みを増してくる。 恋愛経験のないマヤは、こういった話には必要以上に動揺してしまい、自然と声も小さくなる。 「マヤ、あなた速水先生のことが実は気になっているんじゃないの?」 亜弓は確信をこめて続ける。 「それに、あんなに教職に情熱を傾けていたあなたのことだから、今日は初授業のことがもっと話題に上ると思っていたのに、あなたったら、速水先生のことばかりでしょう?」 「亜弓さん、あ、あたしそんなつもりは…仕事をおろそかにしているつもりはないんだけど」 マヤは慌てて否定したが、丁度その時、亜弓の待っていた電車が来てしまった。 するりと乗り込んだ彼女は、いたずらっ子のように笑う。 「来週、また会うでしょ? 速水先生との続き、聞かせてね」 「続きなんて、絶対ないわよ! 気になんてなってないもの!!」 マヤは叫んだが、亜弓を乗せた電車はすでにホームを後にしていた。 |
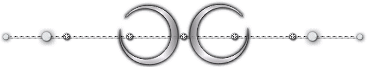 |
長年の夢だった教師になれたマヤにとっては、毎日学校に行くのが楽しみで仕方がなかったが、今朝は歓迎会での失態と亜弓に言われたことが気になって、憂鬱な気分だった。 しかし、社会人となっては、ズル休みをするわけにはいかない。 今日こそは絶対に失敗すまい、と意気込んで早めに家を出ることにした。 バスに揺られながら、気持ちを切り替えて授業のことを考えようとしたが、やはり亜弓に言われたことですぐに頭がいっぱいになってしまう。 (気になってなんか絶対ない!…確かに最初は素敵だと思ったけど…いや、絶対ないわ!!) その時、急なカーブにさしかかって通勤バスが大きく揺れ、考え事をしていたマヤは、うっかりつり革を離してバランスを失った。 そのうえ、周囲の乗客がサッとよけてしまったため、そのままヨロヨロと立ち止まることができずに、一番後ろの座席に座っていた男性の膝の上に尻餅をついてしまったのだ。 「どうもすみません、あたしっ…」 情けなくて、逃げ出したいような気持ちになりながら、マヤはやっとのことで声を出す。 「…まったく」 迷惑そうにゆっくり上げられたその顔は、マヤが今日一番会いたくないと思っていた男性、その人のものだった。 「きみは、また俺に抱きかかえられたいのか。 つり革にはしっかりつかまっていてください、北島センセイ」 速水が心底呆れたように言うそのセリフを受けて、マヤの頭に血がカーッと上った。 「すみませんって言ってるじゃないですか! もう!! こんなことになったのも、全部あなたのせいなんだから…!!」 「俺のせい? どうしてだ?」 「どうしてって…」 マヤは慌てて口を手で塞ぐ。 あなたのことを考えていたせいだなんて口が裂けても言うことはできない。 (意識してるなんて思われたら困る!) 「大丈夫か? 頭は打ってないようだったが…。 衝撃でおかしくなったんじゃないか? ほら、次の停留所で降りるんだぞ」 速水が気軽に頭をポンポンとたたくのは気に入らないが、とりあえずここは我慢しなければ。 紅学園は古くからの閑静な住宅街に囲まれた、なだらかな坂を登った所にある。 30分時間が遅ければ生徒たちでいっぱいのこの道も、いま歩いているのは二人きりだ。 朝の静けさが二人を包む。 桜はもう終わりかけているが、古い屋敷のよく手入れされた庭からは塀を越えてさまざな花が顔を覗かせていた。 「あっハナミズキ。もう咲いているんですね。速水先生は、どんな花が好きですか?」 「花か…俺は良く知らないな。亡くなった母は花を育てるのが好きだったが…」 速水は少し遠くを見るような目をして何かを思い浮かべているのか、そのまま黙り込んでしまった。 口元に軽く笑みを浮かべた、慈愛に満ちたその表情はマヤを戸惑わせる。 おまけに、訪れた沈黙は気まずいものではなく、なんだかとても居心地の良い、自然なものだった。 (こんな表情をする人だったんだ…。なんだかいつもと違うみたい?) 冷血漢にも好きな花なんてあるのかと、意地悪な興味で聞いた自分を恥じて、彼女は俯いた。 「すまない、なんだったかな」 しばらくして速水はマヤの存在を思い出したように言った。 「あの…歓迎会では、送っていただいてありがとうございました」 「あぁ、ずいぶん酔っていたな。まぁ連中も無理させるからな」 「でも…水無月さんは…ちゃんとしてるのに」 「水無月くん? ああ、同じ新任の彼女か」 「あたしだけ、うまく対応できなくて、情けないというか…」 「ひとのことは気にするな。きみはきみなんだ。無理することはない」 自分をかばうような思いがけない優しい言葉に、マヤはしばらく呆然となり、その大きな瞳をさらに見開いて速水を見つめる。 その表情に、その言葉がいつもの自分には似つかわしくなかったと気付き、速水は動揺を隠すように態度を一変した。 「しかし、きみももう学生じゃないんだし、ああいった場でひどく酔ってしまうというのは、考えものだな」 「友達にも怒られました。泥酔して男性に送ってもらうなんてって。 …でも、速水先生が紳士でよかったです。何にもなくて…」 突然、速水が噴き出し、マヤのおどおどした声はかき消された。 「紳士だって? この俺が?? それに…それに…俺が襲うとでも思うのか? 君みたいな…チビちゃんを…」 「もういいです!」 長身を折るようにして笑い続ける速水に、マヤはいたたまれなくなって、瞳に涙を浮かべて駆け出した。 どうしてあんな余計なこと言っちゃったの? 速水先生が私みたいな子供に対して、そんなこと思うはずないのに! あの、ひとをバカにした笑い方! もう!! 穴があったら入りたいくらい…。 その場を去りたい一心で逃げ出したが、しばらくすると慣れないパンプスに足が悲鳴をあげ、マヤは仕方なく立ち止まった。 でも… さっきのあの表情はなんだったんだろ。 冷血漢だって評判だけど、あたしには別の顔が見えるみたい…。 遅咲きの桜を強風が襲い、花びらを散らす。 マヤはそっと振り返ってみたが、桜吹雪が二人を隔てる壁のように立ちはだかり、速水の姿は朧げにしか見えなかった。 <第4話 END> 2006年03月09日 written by shima |
| 登場人物紹介 |
| * back * | * index * | * next * |